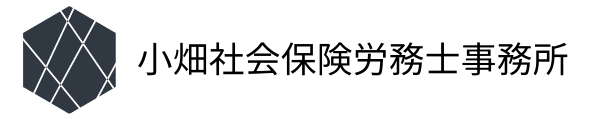本記事で分かること
- ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分確認の流れ
- 給与データ・算定回数のチェック方法
- 変更届・辞退届の提出が必要なケース
- 社労士に代行を依頼するメリット
はじめに
医療機関・訪問看護ステーション各位
すでに ベースアップ評価料(Ⅱ)または入院ベースアップ評価料 の届出を行っている場合、
毎年3月・9月・12月 のタイミングで「区分に変更がないか」を必ず確認する必要があります。
(※6月はベースアップ計画書で確認するため、実質的に不要です)
- 区分が変わっていなければ → 届出不要
- 区分が変わっていた場合 → 地方厚生(支)局長への変更届 が必要(翌月から新しい区分で算定)
- あわせて、変更前区分の辞退届(持参または郵送)も忘れずに提出
対象となる届出
- 医療機関
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
・入院ベースアップ評価料 - 訪問看護ステーション
・訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
今回は 9月の確認タイミング です。
本記事では、実際の 記入例を交えながら、区分確認の流れ・変更届の書き方 を社労士がわかりやすく解説します。
ベースアップ評価料の区分確認・届出でお困りですか?
小畑社会保険労務士事務所が、
医療機関・訪問看護ステーションの区分確認から届出代行までサポートいたします。
書き方と注意点
ベースアップ評価料の区分確認は、
ベースアップ評価料(Ⅱ)を届出している医療機関・訪問看護ステーション が必ず以下の流れで実施します。
区分確認の基本フロー(全員必須)
- 厚労省HPから従来型様式(Excel)をダウンロード
👉 様式はこちら - 職員ごとの給与を確認(賃金台帳・給与ソフトなど)
- 算定回数を確認
- 様式Excelにデータを入力
- 区分に変更があるかを確認
変更がある場合
- 変更届を作成し、3月・9月・12月の月内に地方厚生(支)局へ提出
- 旧区分の 辞退届 も必ず併せて提出
変更がない場合
- 書類提出は不要
- ただし、給与情報と算定回数のチェック結果は必ずExcelに残す
(院内での証跡管理のため、ファイル保管を推奨)
注意点(よくあるミス)
- 給与や算定回数を正しく確認していない
→ 区分変更の有無は必ず「直近の給与データ」と「算定回数」を元に判定する必要があります。勘違いや入力漏れに注意。 - 区分に変更がないのに届出を提出してしまう
→ 本来不要な事務処理が発生します。届出が必要かどうか、まずは必ずチェックを行いましょう。 - 辞退届を忘れる
→ 新旧両方の区分で算定してしまい、返還請求になるリスクがあります。
※変更届はメール提出で構いませんが、辞退届は郵送(持参可)で提出が必要です。ここを忘れるケースが多いため要注意。 - 確認記録を残していない
→ 区分に変更がなかった場合でも、給与情報や算定回数の確認記録は必ずExcelに残しておきましょう。院内監査や局からの照会に備えられます。
実務的なコツ
- 従来形式のExcel様式を必ず使用(最新版を厚労省HPからDL)
- PC入力推奨(訂正印が多いと差し戻しリスク)
- 院内で共有できる形で保管(PDF化や共有フォルダ保存で証跡を残す)
確認の流れ
区分確認では、まず 給与データと算定回数をExcelに入力 し、その結果として「区分に変更があるかどうか」を確認します。
ここで重要なのは 入力 → 判定 → 結果の確認 の流れであり、「変更あり・なし」という結果は確認のあとに分かることです。
ステップ1:給与データを入力
- 職員ごとの直近の給与額を入力します。
- 基準額を満たしているかどうかを確認するための最初のステップです。
ステップ2:算定回数を入力
- 対象期間における算定回数を入力します。
- 算定回数によって区分の判定が変わるため、正確に入力してください。
ステップ3:区分の確認
- Excelの自動計算により、入力した給与・算定回数から「該当する区分」が表示されます。
- その結果を前年の届出区分と照合し、変更が必要かどうか を判断します。
- 「給与」欄に数値を入力
- 「算定回数」欄に回数を入力
- 「判定区分」セルで現在の区分を確認
ポイント
- 区分確認の目的は「変更があるかどうかを確認する」こと。
- あくまで 入力したデータから区分を判定 → その結果を見て変更有無を判断 します。
- したがって、「変更があったケース/なかったケース」と切り分けるのではなく、判定結果を確認すること自体が記入例 です。
記入例

- ここでは外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を想定して記入していきます
- 該当する届け出は「区分変更」算定を行う月は「9月」とします

- 今回は対象従業員を5.0人としてます
- フルタイム4人+20時間のパートさんが二人でも常勤換算で5.0人とします
- 常勤換算は「週所定労働時間」をベースに考えます
- 算定月が9月の場合必要なのは前年9月から今年の8月までの給与総額です
- 賞与と法定福利費を含めた金額(額面)で計算してください

- 全従業員の給与データを入力します
- 図のような形でまとめると分かりやすいです
- 前年9月から今年の8月までの合計額が分かったらそれを総額として計算します
- 表に記入するのは「平均」なので最後に12で割って出た数値を欄に記入します

- 入力し終えた書類がこちらです
- 初診再診回数も「1月当たり」なので6月7月8月の初診再診回数を確認して平均値を算出します

- 入力し終えるとこのような画面が表示されます
- この例だとベースアップ評価料(Ⅱ)1までしか選べませんね
- 今までと同じ区分の場合はここで確認終了です、記録だけ残しておいてください
- 今までベースアップ評価料(Ⅱ)2を適用していた場合などは手続きが必要です
区分変更の流れ
ここでは上記の確認で区分の変更が必要だった場合の流れを解説します。

- 今までに作った書類の他に別添2(一番最初の紙)の欄を埋めます
- 届出区分は「新規」ではなく「区分変更」をタブから選んでください
- ベースアップ新規料(Ⅰ)とベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出である事を明記します
- 各チェックリストにチェックを入れ、届出日、所在地、名称、開設者名を記入します
- これら全てを入力し終えたら管轄の厚生支局長宛にメールで提出します
- 提出先のメールアドレスはこちらのPDFに記載されています
辞退届の提出

- こちらが辞退届になり、区分を変更する際は従前の区分に対する辞退届を郵送で送る必要があります
- Wordのリンクはこちらになります
- 特に難しい所は無いかと思いますが必要事項を埋めて、現在の区分を記入します
- 9月30日まで現在の区分で10月1日から新しいベースアップ評価料(Ⅱ)の区分を適用してください
- 辞退理由は「区分変更の為」で伝わるはずです
おわりに
ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分確認は、毎年 3月・9月・12月 に必ず行うべき重要な手続きです。
確認の流れはシンプルですが、給与データや算定回数のチェックを誤ると、
「本来もらえるはずの点数が算定できない」「逆に返還請求につながる」などのリスクがあります。
本記事では記入例を交えて流れを解説しましたが、
- 日々の業務が忙しくて確認に手が回らない
- 書類の不備や提出漏れが不安
- 自院での管理体制を強化したい
といった場合には、専門家に依頼するのも一つの方法です。
正しく・漏れなく手続きを行い、安心して診療に専念できる体制を整えていきましょう。
✅ 当事務所では、医療機関・訪問看護ステーション向けに ベースアップ評価料の届出代行 を承っております。
是非、下記のフォームから気軽にご相談ください!