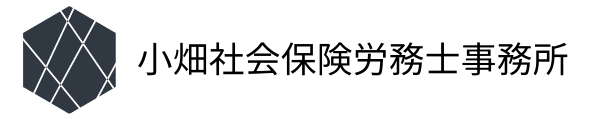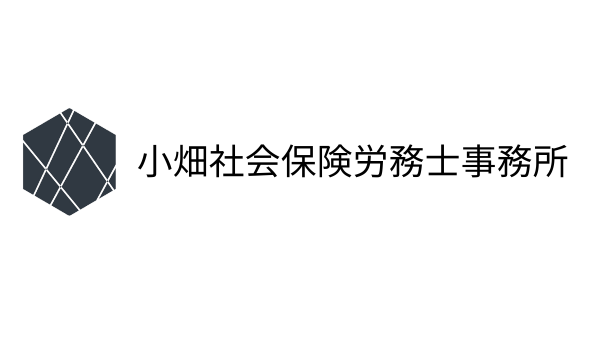2026年から始まる厚生年金・健康保険の適用拡大と企業・パート従業員への影響まとめ
1. そもそも「106 万円の壁」とは
106万円の壁と言われていたのは社会保険の加入基準によるものです。
年収106万円を超えるペースで働くと家族の社会保険扶養から外れてしまい、月9万円働くと月に8万円働くより手取りが減る、1万円分多く働いているのに所得が減るような状態だったため、働き控えを行い、社会保険に加入しなくてもよいように就業調整を行う事が慣行的に行われていました。
現在、社会保険に加入しなければならない人は以下の全てを満たす人です。
- 週20時間以上働く
- 月額賃金8万8000円(=年収106万円)以上
- 従業員51人以上の企業に勤めている
- 学生以外
――この4条件をすべて満たすと、パート・アルバイトでも厚生年金と健康保険に加入する“壁”を越え、手取りが減るため「働き控え」を招いていました。はてなブックマーク
106万円の壁というより「月88,000円」の壁です。
ちなみにこの「月88,000円」に交通費は含まれます。
2. 厚生労働省が示した撤廃案のポイント
| 施行予定 | 改正内容 | 影響 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 年収106万円の要件を撤廃(賃金基準なし) | 約200万人が新規加入見込み オフィスGSR |
| 2027年10月 | “従業員51人以上”の企業規模要件も撤廃 | 企業規模を問わず週20時間以上で加入 |
残る条件は “週20時間以上・2か月超見込み・学生でない” のみ。週20時間未満パートには依然として“新たな壁”が残るとの指摘も。ITAC
3. なぜ撤廃? ── 背景にある3つの課題
- 最低賃金の急上昇で要件が形骸化
時給上昇により月88,000円を超えやすくなったため、壁が機能しなくなりつつある。
東京大阪辺りですと週に20時間働くと月に88000円を超えてしまいますね。 - 慢性的な人手不足
パートが労働時間を抑えてしまい、スーパーなどサービス業で10〜20名の欠員が常態化。 - 将来の年金受給権強化
厚生年金加入による「老後の年金底上げ」で公的年金財政の安定も狙う。
との事ですが、実質的な税金であり、私たちの将来の年金の為だけに使われるのかは少々疑わしいと
言わざるを得ない情勢ですね。
4. パート・アルバイト側のメリット/デメリット
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 手取り月収 | 将来年金が増える | 保険料負担で月々の手取りは▼ |
| 老後年金 | 国民年金+厚生年金の2階建てにアップ | ― |
| 傷病手当金・出産手当金 | 社会保険給付を受けられる | ― |
例)時給1200円、週25h勤務(年収156万円)なら保険料負担は月1.4万円前後だが、将来年金は年間約10万円増える試算となる。
5. 企業側が今から準備すべきこと
- 人件費シミュレーション
保険料負担分(労使折半)を2026年・27年に段階計上。 - 労働時間設計の見直し
“週20h” をまたぐシフトパターンの整理が必須。 - 従業員説明会の実施
手取り減を過度に心配しないよう「給付と将来年金のメリット」を周知。 - 就業規則・雇用契約書の更新
社会保険加入条件・賃金条項を最新化。
6. 今後のスケジュール
| 年月 | 予定 |
|---|---|
| 2024.12 | 審議会了承(済) |
| 2025.秋〜 | 関連法案提出・改正省令公布見込み |
| 2026.10 | 106万円要件撤廃(賃金基準なし) |
| 2027.10 | 企業規模要件撤廃(週20h以上で全国一律適用) |
7. まとめ
- “106万円の壁”は2026年10月に消滅予定。
- 週20時間の新基準が実質的なラインとなり、200万人超が厚生年金・健康保険の対象になる。
- 企業は保険料コストとシフト設計、従業員は手取りと将来年金のバランスを早めに試算しよう。
手取り減より「老後・万一の保障」が上回る場合が大半です。週20時間以上働くパート・アルバイトの方は、保険加入後のメリットを正しく理解してキャリア設計を!
8. 筆者の考察:週19時間“新・壁”問題は解決策になり得るか?
結論から言えば、加入基準を「週20時間」一本に絞っただけでは、
雇用保険とセットでの加入を避けたい心理から、“週19時間30分労働”が新たな就業調整ラインとして定着する可能性が高いと考えられます。
雇用保険も週20時間で加入義務が発生するため、企業としては
「社会保険+雇用保険のダブル負担」を避ける動きが起きやすく、
結果的に、“20時間未満に抑える”雇用設計が常態化するリスクがあります。
また、最低賃金の上昇により、「月額8万8000円」という賃金基準はすでに形骸化しています。
この状況で時間基準だけを残す制度設計にした場合、むしろ労働時間の圧縮が進むことにもなりかねません。
◆ 本気で労働力を確保したいなら「低所得者の保険料軽減」が必要
本来の目的が「パート・アルバイトの就業促進」であるならば、
制度設計は**“働き控えの原因”に正面から向き合う必要があります**。
その原因は明白で、一定ラインを超えると手取りが減るからです。
したがって、今後検討すべきは以下のような施策です。
- 月額報酬が一定未満(例:10万円以下)の場合、社会保険料率を段階的に軽減
- **給付付き税額控除(EITC)**など、手取りを逆転させない再分配制度の導入
- 雇用保険と社会保険を**“同時に加入させる制度”にするなら、セット割引のような保険料設計**も選択肢に
現行制度のままでは、「就業促進」どころか**“新たな壁”を作ってしまうだけ**という懸念は、拭いきれません。
お問合せ
就業調整、就業規則など
お悩みがございましたら是非気軽に下記のフォームよりお送りください。