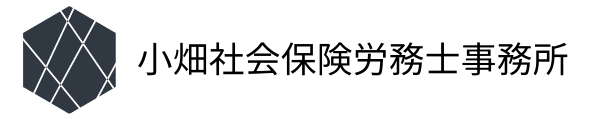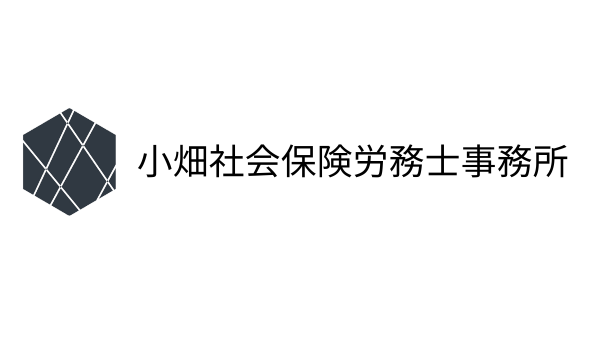はじめに
2024年度は、労働基準法、社会保険制度、フリーランス保護法など、多岐にわたる法改正が実施されました。これらの改正は、企業の労務管理や人事制度に直接影響を及ぼすため、適切な対応が求められます。本記事では、主要な改正点を時系列で整理し、実務上の対応ポイントを解説します。
2024年4月施行の主な改正
1. 労働条件明示の義務化強化(労働基準法施行規則の改正)
労働契約締結時の明示事項に以下が追加されました:
- 就業場所および従事すべき業務の「変更の範囲」
- 有期労働契約の「更新上限の有無と内容」
- 無期転換申込機会の明示
- 無期転換後の労働条件の明示
これらの明示は、書面または電子メール等で行う必要があります。特に、有期契約労働者に対する更新上限の明示義務は、契約更新時にも適用されるため、注意が必要です。
2. 裁量労働制の見直し
専門業務型裁量労働制の対象業務に「M&Aアドバイザー」が追加され、適用要件として労働者本人の同意が必要となりました。また、企画業務型裁量労働制についても、労使委員会の開催頻度が6ヶ月以内ごとに1回とされるなど、制度の厳格化が図られています。
3. 時間外労働の上限規制の適用拡大
建設業、自動車運転業務、医師、鹿児島・沖縄県の砂糖製造業に対する時間外労働の上限規制が適用されました。これに伴い、自動車運転者の拘束時間等を規制する改善基準告示も見直されています。
4. 化学物質管理の強化(労働安全衛生法の改正)
危険性や有害性が確認された化学物質234物質が新たに規制対象に追加されました。また、化学物質を取り扱う事業者には、化学物質管理者および保護具着用管理責任者の選任が義務づけられ、衛生委員会の付議事項にも化学物質管理が追加されました。
2024年10月施行の主な改正
5. 社会保険の適用拡大
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大され、従業員数が51人以上の企業も対象となりました。対象となる短時間労働者の要件は以下の通りです
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 学生でないこと
- 雇用期間が2ヶ月を超える見込みがあること
これにより、企業は対象となる短時間労働者を社会保険に加入させる手続きが必要となります。
2024年11月施行の主な改正
6. フリーランス保護法の施行
フリーランスに業務委託をする事業者に対し、以下の義務が課されました:
- 取引条件の書面等による明示
- 報酬の支払期日の規制
- 募集情報の的確表示
- 育児・介護等への配慮
- ハラスメントに係る体制整備
- 中途解除の事前予告
これにより、フリーランスで働く者の保護が強化されました。
2024年12月施行の主な改正
7. 健康保険証の新規発行終了とマイナ保険証への移行
2024年12月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が進められました。既存の健康保険証は、有効期限まで使用可能ですが、転職や引っ越し等で保険資格が変わった場合は、マイナ保険証の利用が基本となります。デジタル庁
2025年1月施行の主な改正
8. 離職票のマイナポータル直接交付
2025年1月20日から、離職者本人が希望し、離職手続を電子申請で行うなどの利用条件を満たせば、雇用保険被保険者離職票が本人のマイナポータルに直接交付される仕組みが導入されました。
まとめ
2024年度は、多くの労働・社会保険関連の法改正が実施され、企業の労務管理に大きな影響を与えました。各改正点を正確に把握し、適切な対応を行うことが求められます。特に、労働条件明示の義務化強化や社会保険の適用拡大、フリーランス保護法の施行などは、企業の実務に直結する重要な改正です。これらの改正に対応するためには、就業規則の見直しや社内制度の整備が必要となる場合があります。必要に応じて、専門家への相談を検討しましょう。
※本記事は、2025年5月21日時点の情報に基づいて作成しています。最新の法令や制度の詳細については、厚生労働省の公式サイトなどでご確認ください。
法改正、対応できていますか?
- 就業規則の更新、まだ手つかず…
- フリーランスと契約してるけど対応方法が不明…
- 社会保険の対象者、誰が該当するか分からない…
そんな場合は “今すぐ” 対応が必要です。
法改正に対応してないと罰則や、行政指導のリスクも…