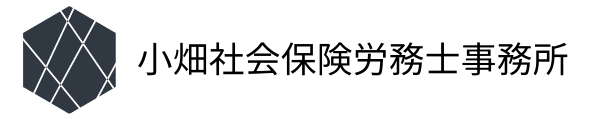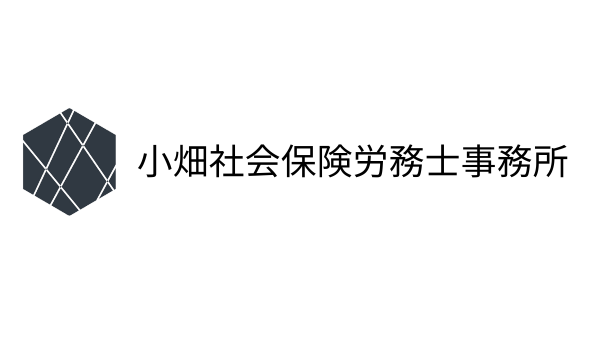はじめに
高齢化の進展とともに、仕事と介護の両立は、企業にとって避けては通れない課題となっています。
2024年5月に成立した改正育児・介護休業法では、「介護」に関する制度が大きく見直され、2025年4月1日から順次施行されます。
今回は、その【介護編】として、実務に関わる社労士や企業担当者が押さえておくべき改正ポイントを解説します。
育児編はこちらから!
■ なぜ今「介護支援制度」の強化が必要なのか?
- 労働力人口は今後減少が加速。2035年には最大600万人、2040年には900万人の減少が予測されています(低位シナリオ)。
- 介護が原因の離職者は毎年10万人超。今後、企業にとって人材確保の観点からも対策が不可欠です。
【主な改正ポイント(2025年4月1日施行)】
① 介護離職を防ぐための「個別の周知・意向確認」の義務化
- 労働者が「家族の介護が必要になった」と申し出た場合、企業は介護休業・介護休暇・短時間勤務制度などの内容を個別に周知し、意向を確認する義務が発生します。
- 周知方法は、文書でも口頭でもOK。申出先や対応者を明確にしておくとスムーズです。
- 制度の利用を抑制するような言動(不利益示唆等)は禁止されています。
② 40歳前後での情報提供の義務化
- 「労働者が40歳になる年度」または「40歳の誕生日から1年間」に、企業は介護支援制度等の情報提供を行う義務があります。
- これは、介護保険の被保険者となるタイミングであり、親の介護が始まり得る年齢でもあるため。
- 集団説明やリーフレット配布も可。内容には、以下を含めることが望まれます:
- 介護休業制度(体制構築のための休業)
- 介護休暇制度(通院付添など日常的な介護に対応)
- 短時間勤務など柔軟な働き方
③ 雇用環境整備の義務化(4項目のうち1つ以上)
- 制度を利用しやすくするために、以下のいずれかを講じる必要があります:
- 介護制度に関する研修の実施
- 相談体制の整備(窓口設置など)
- 社内の制度利用事例の紹介
- 制度利用を促進するための方針の周知
※複数実施が望ましく、全事業主が対象です(介護者が現在いなくても義務あり)
④ 介護休暇を取得できる対象者の拡大
- 労使協定で「継続雇用6か月未満の者」を対象外にできていましたが、これが廃止されます。
- 入社間もない社員も、必要があれば介護休暇を取得可能になります。
⑤ 介護のためのテレワーク導入(努力義務)
- 常時介護を必要とする家族がいる場合、労働者がテレワークを選択できるよう配慮することが企業の努力義務に。
- 業務上の制約がある場合は、対象を限定することも可能ですが、導入に向けた前向きな対応が求められます。
⑥ 「常時介護を必要とする状態」の判断基準を見直し
- 対象家族に年齢制限はなく、判断基準の緩和により、障害児や医療的ケアを必要とする家族も対象となるよう整理されました。
- 提出書類の例として、「障害支援区分認定通知書」「障害児通所給付費支給決定通知書」なども追加。
- 証明書類の提出がないことを理由に制度利用を拒否してはならない点に注意。
【中小企業向け支援制度の見直し(予定)】
法改正にあわせて、厚生労働省が所管する「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」についても、令和7年度当初予算案において見直しが盛り込まれています(※今後変更の可能性あり)。
現時点で示されている主な変更点は以下のとおりです。
介護休業の取得要件:
「合計5日以上」→「連続5日以上」に変更予定
助成金の支給タイミング:
「取得時+復帰時(分割)」→「復帰時に一括支給」へ変更予定
支給額の算定方法:
「制度1つ導入+1人利用で一律支給」→「制度導入数や利用日数に応じた段階的支給」へ見直し予定
代替要員に関する支援:
業務代替者の確保・手当支給については、従来の加算措置から独立した支給対象となる見込み
※今後、制度内容が確定次第、詳細が発表される予定です。
まとめ:企業に求められるのは「制度の整備」ではなく「使える環境づくり」
今回の改正では、単なる制度整備にとどまらず、社員が安心して制度を活用できる職場環境づくりが求められています。
加えて、個別周知や雇用環境整備など、“義務”として対応しなければならない項目も多く含まれている点に注意が必要です。
社員が制度を“使える”環境をつくることが法改正の本質です。
- 対応しないと、行政からの指導対象となる可能性もあります。
- 就業規則の変更、個別周知の方法、社員研修…やるべきことは多岐に渡ります。
対応に不安がある企業様は、まずはお見積りからでもお気軽にご相談ください!
当事務所で対応している主なサポート内容
- 就業規則・労使協定の見直し支援
- 制度周知・社内研修の企画・運営
- 両立支援等助成金の提案・申請サポート
- 個別相談対応や社内体制整備の助言
また、育児編はこちらで解説しております!
ご相談はお気軽に
改正対応や制度整備でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
実はこの改正、放置しておくと“未対応”として行政から是正指導の対象になる可能性もあります。
「うちは対象じゃない」と思っていても、実は“対応必須”というケースも少なくありません。
まずはお見積りだけでも大歓迎です。
手遅れになる前に、早めのご相談をおすすめします。